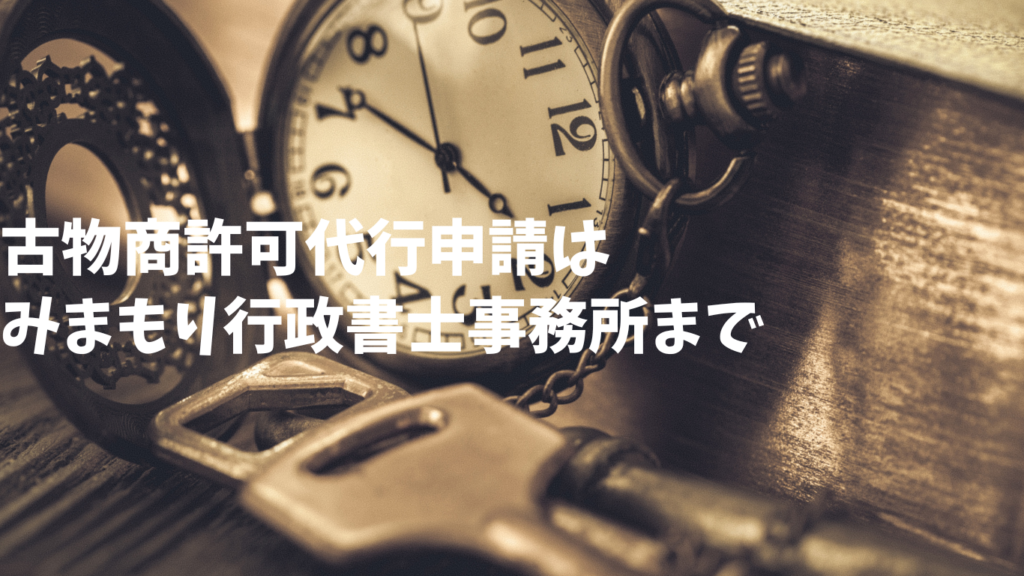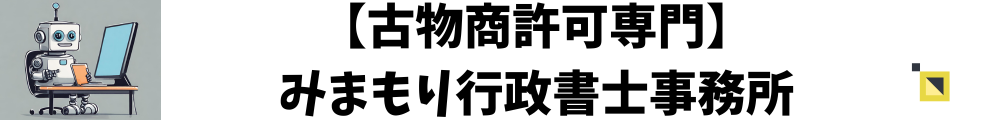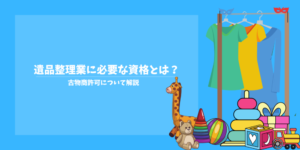中古のお酒の販売に必要なのは古物商許可?

中古のお酒の販売に必要なのは古物商許可?
Contents
1.お酒の買取や取引に必要な許可とは?古物商?
①中古の酒の取引が増えてきている

ポイント:中古のお酒が持ち込まれたらどうする?
近年、リサイクルショップや買取専門店で「中古のお酒」を取り扱うケースが増えています。
また、インターネットやオークションサイトでの取引も活発になり、希少価値の高いウイスキーやワインが高値で取引される場面もテレビなどでよく見られるようになりました。
こうした背景から、「自分が行なっている古物商のお店でもお酒の買取や販売を始めたい」と考える方も少なくないでしょう。
では、お酒が中古品だからと言って、古物商として取り扱っていいのか疑問に思いませんか?
今回の記事では古物商でお酒を販売することについて、解説していきます。
②お酒の買取・販売に古物商許可が必要?

ポイント:お酒は古物の分類に該当しない
まず、多くの方が疑問に思うのが「お酒の買取や販売に古物商許可が必要かどうか」という点です。
結論から言うと、原則としてお酒の買取や販売には古物商許可は不要です。
古物商許可が必要かどうかは、取り扱う商品が「古物」に該当するかで判断しますが、お酒は法律上「古物」の分類に含まれません。そのため、お酒の取引を行う場合は古物商許可は必要ありません。
ただし、例外的にお酒の容器やボトルそのものに価値がある場合(例:デザイン性の高いボトルやコレクターアイテムの瓶)は、「容器」を古物として扱う可能性があります。この場合は古物商許可が必要になるケースもあるため、判断に迷った際は警察署の生活安全課に相談すると安心です。
ポイント:お酒の買取は免許不要
酒税法では「販売業免許」についての規定はありますが、「購入するための免許」という規定はありません。つまり、酒類を購入する場合には特別な免許を取得する必要はありません。
これは、一般の消費者が自分で飲むためや贈答用としてお酒を購入する際に、免許が必要ないのと同じ考え方です。
ポイント:お酒の販売は酒類販売業免許が必要
仕入れたお酒を販売する場合には「酒類販売業免許」が必要です。
ただし、自宅にあるなどの不用品のお酒を販売する場合には酒類販売業免許は必要ありません。
お酒を仕入れて販売するなど継続的に事業を行う場合には、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。
また、店頭で販売するのか、インターネットで販売するのかなどの販売方法やお酒の種類によって、取得しないといけない免許が変わってきます。
全てを説明すると長くなってしまいますので、例として
国産ウイスキーを販売する場合
に必要なことを次項から解説していきます。
2.国産ウイスキーを販売する方法

①国産ウイスキーを店頭で販売する場合
ポイント:店頭で販売する場合には一般酒類小売業免許
リサイクルショップや買取店で店舗販売を行う場合は、「一般酒類小売業免許」を取得する必要があります。
この免許を持っていれば、国産ウイスキーに限らず、全ての種類のお酒を店頭で販売することが可能です。
日本酒、ビール、ワイン、海外産のお酒でも、なんでもOKです。
②国産ウイスキーをインターネット上で販売する場合

ポイント:通信販売種類小売業免許を取っても
国産ウイスキーは販売できない!
2都道府県以上の消費者に対してインターネットを通じてお酒を販売する場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
ただし、この免許では原則として、国産酒の販売はできません。
通信販売種類小売業免許を取得したとしても販売できるお酒は下記のみです。
通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒
- 輸入酒類
- 海外で製造されたお酒
- 課税移出数量が3,000kℓ未満の酒類製造者のお酒
- 地方の特産品を原料としたお酒など(国産も可能)
この点は注意が必要です。
ただし、インターネットで国産ウイスキーを販売できる方法は他にあります。
ポイント:1都道府県のみでインターネット上で販売する

1都道府県のみであればインターネット上でも「一般酒類小売業免許」で販売が可能です。販売対象を店舗所在地と同じ都道府県内の消費者に限定するということです。
例えば、オークションサイトでの出品時に「〇〇県内のお客様限定」と明記し、落札者が他府県の方であれば販売を断るといった対応が必要です。この方法であれば、サントリーやニッカといった大手国産酒の販売も可能です。
ポイント:インターネット上で申し込みを受け、店頭で販売する
インターネット上で申し込みを受けて、店頭で酒類を引き渡す場合は「一般酒類小売業免許」で販売が可能です。
この場合、2つ以上の都道府県でインターネット上で販売しても問題ありませんが、お客様に店頭に来てもらわないといけないという意味では、現実的ではないでしょう。
3.酒類販売業免許の取得するには

ポイント:様々な許可要件のクリアが必要
酒類販売業は誰でも始められるわけではありません。
酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。
これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。
酒類販売業の免許取得要件
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 需要調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
ポイント:需要調整要件が必要 → とりあえず取得は不可能
間違いやすいポイントなのですが、「副業のために酒類販売ができると良いからとりあえず免許持っておくようにしよう」ということはできません。
酒販免許を取得するには、具体的な計画と実現性が求められます。
「どこから、どのようなお酒を仕入れて、どこで、どれくらい、いくらで、いつから販売したいのか」ということがはっきりしていないと免許の取得ができないということです。
ポイント:酒類販売のことについてもっと詳しく知りたい場合は
酒類販売免許のことについて、もっと詳しく知りたい場合には下記のページからご確認ください。当事務所でも申請代行を行なっています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可能 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください
3.まとめ
以上、酒類を販売する際に必要な免許について解説させていただきました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな面倒な古物商許可の申請は
【古物商許可専門】
みまもり行政書士事務所

にお任せください!
当事務所では古物商許可を申請代行しております。
個人の方はもちろん、法人での申請も対応可能です。
即日申請させていただきますので、お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可能 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください
併せて読みたい記事